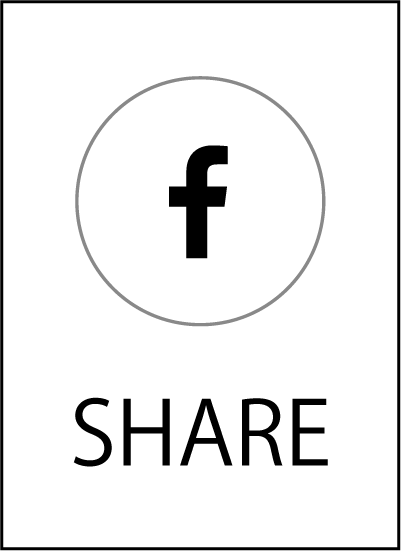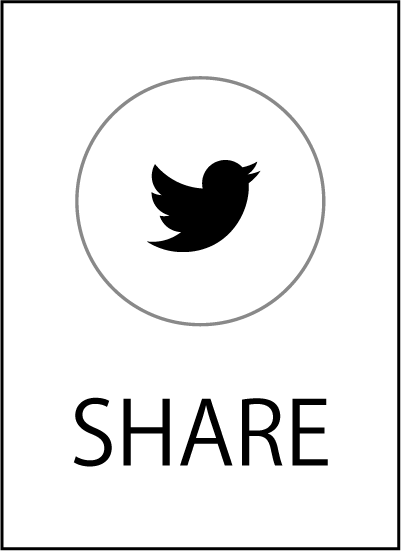2025年11月10日、ベルギーのデザイナー・イネ・レイラントさんとコラボレーションした作品が完成します。
その名も、ベルギーのデザイナー・イネさんがみた にほんの『きせつのたべもの』4冊セット。
イネさんは日本に強く惹かれ、長年にわたり日本文化を研究。ベルギーと日本を行き来して活動する新進気鋭のアーティスト。
謙虚で慎ましい姿勢を持ちながらも、大胆な好奇心とひたむきな研究心を併せ持った表現者です。
今回、この作品づくりを通して、私たちがお聴きしたかったことを伺いました。
11の質問に対するイネさんの知性に溢れた言葉は、作品とは異なる角度から多くの刺激を与えてくれます。
ベルギーに生まれた素晴らしいアーティストが日本を愛してくれたこと、そして私たち戸田デザイン研究室を見つけてくれたことに溢れる感謝を込めて…。
イネ・レイラントさんのインタビューをお届けします。
★作品の詳細はこちらから
ー 私は新しい街や国を旅するたびに、地元の本屋を訪れるのが大好きです。
日本では、特に絵本コーナーに惹かれます。児童書は日本文化において非常に重要な位置を占めており、多くの書店が素晴らしい品揃えを誇っています。
いつものように、目に留まった本を手に取って作者や出版社を確認すると、それが戸田デザインであることに何度も気づきました。彼らの作品は独特の色彩と明快さを持ち、すぐに私の心に響きました。
いつか彼らと一緒に本を作りたいという思いが芽生え始め、ついに勇気を出して連絡を取りました。
■戸田デザインとの仕事はいかがでしたか? 私たちは頑固なことで知られていますが…。
ー 確かに長いプロセスでしたが、この本を一緒に作り上げるのは本当に楽しかったです。
初めてお会いした時から、私たちは同じ価値観を共有していると感じました。
特に、真に美しいものを作るには時間をかける価値があるという信念です。
戸田デザインが頑固だと言われる理由も分かります。
確かに彼らは厳格で、どんなことにも目を光らせます。
でも、正直に言って私はそれがとても好きでした。
彼らが細部に至るまで、どれほどの配慮と気配りを注いでいるかがよく分かりました。
この本は私にとって大切なものであると同時に、彼らにとっても大切なものであるように感じました。
おかげで、プロセス全体が真のコラボレーションのように感じられたのです。
共通した献身的な思いが、この経験全体をとても特別なものにしてくれました。
■あなたが日本文化に興味を持ったきっかけは何ですか?
また、日本のどんなところに惹かれるのですか?
ー 私が最初に日本に興味を持ったのは建築でした。
安藤忠雄や隈研吾といった建築家の有名な建築物だけでなく、1970年代や80年代の古い古民家や、ごく普通のアパートにも惹かれました。
グラフィックな雰囲気、考え抜かれた色使い、そして古いものと新しいものが融合している点に魅了されました。
日本を深く知るにつれ、私の関心は徐々に外から内へと移っていきました。
人々の家、日常生活、そしてキッチンへと。
日本の文化で私が最も惹かれるのは、細部に至るまでの細やかな配慮と気配りです。
お土産の美しい包装、本の丁寧な包装、料理の盛り付け方など、あらゆるところに配慮が行き届いています。
その静かな献身的な姿勢に、私は感銘を受けています。
■日本の食べ物を描いて、何か発見はありましたか?また、どのような困難がありましたか?
ー 日本で最初に発見したことの一つは、旬の野菜の種類の多さでした。
初めて日本に来た時は、ごく一般的な野菜しか知りませんでしたが、それ以上にもっと広い世界があるんです。
旬の野菜を食べることで、味・形・色など実に様々な野菜に触れることができ、今まで知らなかった食材を知ることは、とても刺激的でした。
最大の課題は、それぞれの食べ物が認識できるようにしながら、より抽象的な描画スタイルを貫くことでした。
形をシンプルに描くのは大好きですが、その本質は失いたくありませんでした。
戸田やすしさんは、物事を正しく敬意を持って描くことはもちろん、自分の視点も大切にすることを教えてくれました。
そのバランスを見つけるのは、時に困難を要する作業でした。
■どのようにして、今のシンプルなスタイルにたどり着いたのですか?
ー 私は応用美術とイラストレーションを学びましたが、在学中から伝統的なスケッチよりも構図や色彩に興味を持っていました。
シルクスクリーン印刷に多くの時間を費やし、それが私の思考を大きく形づくりました。
シルクスクリーン印刷は、色彩の相互作用や、どのように層を重ねてイメージを構築していくかに自然と焦点を当てられる技法です。
そしてここから少し技術的な話になりますが、シルクスクリーンのフィルム制作に写真や既成の画像は使用しませんでした。
代わりにスクリーンに直接テープを貼ったり、切り抜きフォームを使って形を作りました。
この手法によって、私はあらゆるものをシンプルにし、非常にグラフィックな視点で考えるようになったのです。
時が経つにつれ、このアプローチは私のスタイルの基盤となりました。
それは、クリーンで明確、そして本質に焦点を絞ったものです。
■あなたの特徴である色彩について考えるとき、どんなことに注意していますか?
ー 私にとって、色彩を扱うことはとても自然で直感的なものです。
完全に学んだり説明したりできるものではなく、むしろ感覚に近いものです。
自然、古い建物、グラフィックポスターなど、あらゆる場所で興味深い色の組み合わせに常に気づきます。
日常生活は、気づかないうちにインスピレーションに満ちていることが多いのです。
新しいプロジェクトを始めるとき、まず最初に考えるのは色です。何かを描く前に、使いたいパレットが明確に決まっています。
今回のプロジェクトでは、それぞれの季節に独特の雰囲気とムードを与えつつ、それぞれの本がセットとして調和していることが特に重要でした。
■尊敬するアーティストや影響を受けたアーティストはいますか?
ー イラストレーターとして、ディック・ブルーナとチャーリー・ハーパーの作品に初めて魅了されました。
シンプルなフォルムとすっきりとした線で、これほど美しいイメージを描き出す彼らの力に、本当に感銘を受けました。
何の苦労もなく描かれているように見えますが、その力強さは計り知れません。
色彩に関しては、スーザン・フレコンやエテル・アドナン、イルゼ・ドホランダーやルース・ファン・ビークといった、思慮深く予想外の方法で色彩を使うアーティストからインスピレーションを受けています。
私にとってもう一つ大きな影響を与えてくれたのは、ベルギーの彫刻家ポール・ジースです。彼の作品はいつも私を感動させてくれます。
彼はもっと国際的に知られるべきだと思っています。
日本で熊谷守一を発見できたのは、本当に嬉しかったです。
東京にある熊谷守一美術館は大好きで何度も訪れていますが、その度に刺激を受けています。
そしてもちろん、田中一光さんの作品も本当に素晴らしいですね。
■この作品は、イネさんの視点から日本の文化を再発見できます。
イネさんご自身は、他の国の文化から何を学びましたか?
ー もちろん、どの国にも魅力的な文化があり、地球上には数え切れないほどの興味深い物語が存在します。
しかし、文化は深く掘り下げなければ面白くなりません。
様々な国を旅するのが好きな人もいますが、それでは訪れた文化の表面的な部分しか理解できず、残念なことです。
だからこそ、私はできるだけ多くの国について学ぼうとするのではなく、一つの国に焦点を当てて深く研究するようにしています。
私は日本を選び、他の多くの文化を見るのではなく、日本の文化を研究し続けています。
もちろん、私はヨーロッパ人なので、どこへ行ってもそのバックグラウンドを背負っています。
それが必然的に私が日本をどう見るか・そこで発見したものをどのように解釈するかを形成し、多様な視点が混ざり合うことで、より豊かな経験になるのだと思います。
■あなたの国について教えてください。
ーベルギーは魅力的な国です。小さいながらも、非常に複雑な文化圏を持っています。
公用語はオランダ語、フランス語、ドイツ語の3つです。オランダ、フランス、ドイツという3つの主要国と国境を接しているため、ベルギーは常に文化と文化交流の中心地であり続けています。
オランダの起業家精神、フランスの美食と芸術的な洗練、そしてドイツの勤勉な精神が融合しています。
私は芸術で知られる歴史ある街、アントワープで生まれ育ちました。画家ルーベンスの故郷であり、世界有数のファッション学校を誇ります。また、ヨーロッパ最大級の港町でもあります。
私の芸術に対する考え方や姿勢は、故郷アントワープに深く影響を受けていることを認めざるを得ません。
アントワープは住みやすい街でもあります。
物価も比較的手頃です。街が大きすぎないので、ほとんど徒歩か自転車で移動できるで日常生活がとても便利です。
友達も近くに住んでいるので、ふらっと会ってコーヒーを飲むのも簡単です。
こうした親近感やアクセシビリティの良さは、私にとって大切なことです。
■今、あなたが一番興味を持っているトピックは何ですか?
ー旬の食材をテーマにしたこの本の制作を通して、このテーマへの愛がさらに深まりました。
最近は特に和菓子に興味があります。
和菓子は驚くほど多様性に富んでいて、地域や季節ごとに独特の名物があり、そこには美しい物語が隠されていることも少なくありません。
もっと地域や都道府県の特色ある和菓子を探して、描いていきたいと思っています。
日本には隠れた名物がたくさんあり、それらを見つけるのは宝探しのような気分です。
■この本を読む人たちに伝えたいメッセージはありますか?
ー日本で活動するヨーロッパ出身のアーティストとしてこの本を制作したことで、周りの世界に対する全く新しい視点を得ることができました。
何かを「新しい目」で見ることで、普段は見落としがちな細部に気づくことができるというのは実に興味深いことです。
日本には、食に意味を与える多種多様で独特の方法があります。他の国では旬の食材は比較的限られていることが多いですが、日本では毎月特定の食材が使われています。これが日本食の豊かさを支えています。
日本の食文化を大切にしていく。この本を通して、子どもたちと親御さんに、その気持ちを伝えたいと思っています。
文化は脆く、忘れられやすいものです。
この本が日々の食の美しさへの好奇心や感謝の気持ちを少しでも呼び起こすきっかけになれば、大変嬉しく思います。
ーーーーーー
【プロフィール】
Inge Rylant(イネ・レイラント)
ベルギー・アントワープ出身のイラストレーター兼ヴィジュアルアーティスト。ヨーロッパと日本を行き来しながら活動を行う。
大胆な色使いと装飾を排した図形を用いて、独自の視覚言語を長年に渡り構築。
クリーンなデジタル描画による抽象と具象を合わせもつ作品が特徴で、色や構図といったイメージの基本となる要素に焦点があてられている。
書籍や雑誌にイラストレーションを提供したり、デザインやテキスタイルのブランドとのコラボレーション等に加え、自主制作作品の発表も精力的に行う。