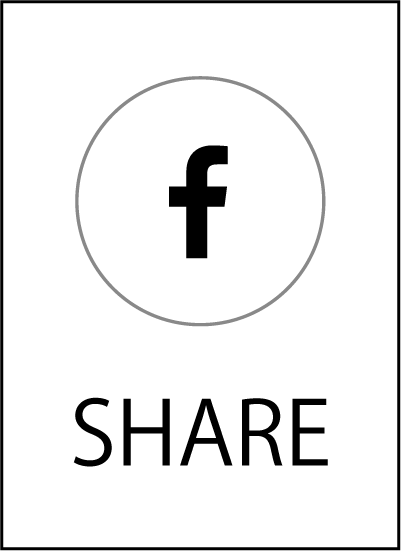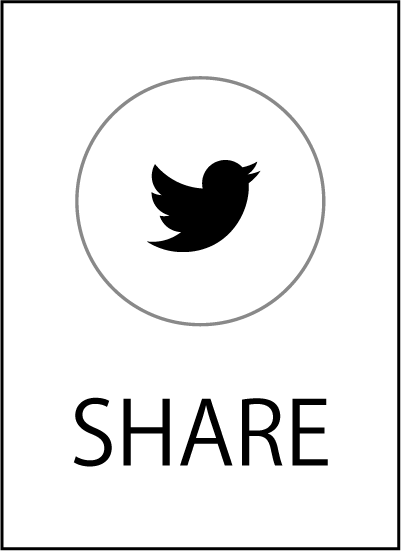私たち戸田デザイン研究室は「知育えほんの草分け」と評していただくことがあります。
自分たちでも恐縮してしまう程の言葉をいただいて、大変有り難く感じています。
確かに私たちの作るモノは、子どもたちが知識に触れるためのものばかり。「知育」にカテゴライズされるのは自然な流れとも言えます。
しかし、いざ「知育」の枠の中に入ると、まるで自分が入る教室を間違えてしまったような、どことなく落ち着かない感覚があるのも事実です。
このムズムズとした感覚を言葉にしようとしても、正直、なかなか難しい…。
しかし、この感覚があるからこそ、戸田デザインの作り出すモノや考えに共感くださる方々がいらっしゃる。そんな嬉しい手応えも感じてきました。
一体、私たちは何にムズムズとしていると言うのか。
どんな思いで子どもたちの学びに関するモノづくりをしてきたのか。
今まであえて深く踏み込まずにきたテーマについて、代表・作り手である戸田靖の考えを聞いてみました。(聞き手:広報 / ディレクター 大澤)
【目次】
あえて、語ってみよう。
ー いきなりですが、今日は戸田デザイン研究室の考える「知育」や「学び・教育」について、いつもより深く掘り下げていきたいと思います。
戸田:また難しいところを掘るつもりだね 笑。
ー そうですね 笑。
弊社の商品は大きく「知育」というジャンルに分けられます。
しかし、会社の理念として【単に知識を伝えるだけの教育教材を作っているつもりもない】と言っています。
いわゆる“お勉強”のモノを作っているわけではないと、わざわわざ宣言している訳です。
戸田:はい。【私たちが届けたいのは、知識を超えた「心の動き」=感性です】とお伝えしてきました。
ー そのあたりの考えなどは、この自社サイトや店頭のフェアなどでもお伝えする機会をいただてきましたよね。
でも、この弊社独自の考えをもう少し本音でお伝えしたい。しかし、これがなかなか難しくもあり…。
戸田:慎重に言葉を選ばないと、誤解も生みやすいテーマでもあるしね。
ー さらに、弊社は最終的には作ったモノが全てというか。
最も雄弁に語るべきは作品とすることで、あえて複雑な説明をしていない部分もありませんか?
戸田:それはモノを作る側である、私の考えに基づいていると思います。
自分が作ったモノの魅力。それを説明で補ってもらうことでしか伝えられないなら、モノ自体の完成度が足りない。
モノだけでもしっかりと魅力を伝えられるような仕事をするべきだと、肝に銘じてきたからね。
ー 大前提としてお客様をはじめ、受け手がどう感じるかは自由です。
発信側である我々の考えを一方的に押し付けてはいけないと思っています。
ただ自分たちの言葉で伝えていくという行為も、作品を作るという行為も本質的には同じではないでしょうか。
伝えたいことがあって、最良を目指し、責任を持って届けるという意味では…。
戸田:それはそうだね。
会社のWebサイトを作ってまだ10年足らずだけど、こちらの考えを自分たちの言葉で伝えることで、お客さまに戸田デザインそのものをより深く理解してもらえていると思います。
難しいけれど、この機会に色々話してみましょう。
自分の頭で考え、心豊かに生きる。
ー 戸田デザインのモノづくりは、1982年に『あいうえおえほん』を出版したことから始まりました。
それまでフリーデザイナーとして様々なデザインを手がけていた戸田幸四郎(1931-2011)が、長く残っていくものを作りたいと企画・制作・出版。
おかげさまでミリオンセラーとなり、2019年にはグッドデザイン賞も受賞。弊社の原点にして代表作です。
戸田:たくさんの方に読んでいただいて、本当に嬉しい限りです。
ー 今回、改めて注目したいのが、推薦文をお寄せくださった無着成恭先生の存在です。
出版物の帯や推薦文をどなたに書いていただくかも、その本を表すポイントではないかと思うのですが。
戸田:確かにそうですね。
無着成恭先生は教育者・僧侶として、戦後の民主主義教育の実践に取り組まれた方でした。
大人気だったTBSラジオ番組「全国子ども電話相談室」の回答者も長く務められていました。
ある世代から上の方は、あの独特の優しい語り口調を覚えていらっしゃる方も多いと思います。
ー 著名な教育者でいらした無着先生に、なぜ推薦文を書いていただけることになったんでしょう?
戸田:戸田幸四郎の兄・戸田吉三郎が無着先生を紹介してくれたんです。
無着先生と吉三郎は同級生。二人とも故郷・山形の師範学校に通っていました。
卒業後は無着先生は教育者に、吉三郎は画家にと別々の道を進みましたが、ご縁は続いていたようで。
無着先生は子どもたちが自分の言葉で綴る・伝えるということにも、大変な力を注いだ教育者としても知られています。
弟がこの絵本を出すのなら、無着先生に見てもらってコメントをいただくのが一番だろうと考えたんだと思います。
ー そして、推薦の言葉を寄せてくださったんですね。
ーーーー
■推薦の文このような コトバと文字を学ぶ 子どもの絵本にとって もっとも大切な条件は
1、単純明快であること
2、色に濁りがないこと
3、実物と対応できること である
とくに 実物とコトバと絵が 頭の中で統一したとき 子どもはまんぞくするのだ
ということを忘れずに つくらなければならない
この絵本は その条件をみたしている
無着成恭(僧侶・教育家)
ーーーー
ー 改めて無着先生に関する資料や書籍、インタビューなどを拝見すると、子どもたちの教育に対して強い信念をお持ちであったことが伺えます。その強さたるや、凄まじいものがある。
これは、戦争を経験されたことが大きく影響しているのではと感じます。
戸田:無着先生が師範学校を卒業して教員になったのは、戦後間もない頃です。
志を持って教師を目指していた方にとっても、苦しいことだらけだったでしょう。
ー あるインタビューで無着先生が仰っていましたが、師範学校時代にアメリカの教育使節団の報告書をご覧になったそうです。
そこには政治に教育が縛られず、自由な空気のもとで子どもの教育が行われるべきとあったそうで、これにとても衝撃を受けたと。
戸田:戦争は、教育も子どもたちも呑み込みますからね。
ー さらに無着先生は、子どもたちが疑問に思う心を大切にするべきとも仰っていました。
例えば分数の割り算をする時に、割る方の分数の分母と分子をひっくり返す訳ですが、「これはなぜ?」と子どもたちが思えること。そして教師もそれに応えられることが重要だと。
学びというのは覚えるものではなくて、自分の疑問を示せる環境があり、自分の頭で考えていくことが大切という主旨のお話をされていました。
これはやはり、政治=戦争に教育が呑まれていく時代を経験した方の強い思いから発せらていると思います。
戸田:私の父でもある戸田幸四郎は、15歳で終戦を迎えました。他の多くの子どもたちと同様に、軍国主義の教育を受け、日本の勝利を信じて疑わない少年だったそうです。
連日新聞では日本が勝利すると伝えていましたが、一転して敗戦を迎えた。
昨日まで軍国主義を唱えていた先生たちの中には変わり身の早い人もいて、人も新聞も信じられなくなったと残しています。
ー 戦争がもたらす恐ろしさは、ひとつだけではありません。いわゆる同調圧力がかかることはもちろん、憎しみを助長するような誤った情報も流布する。これは今の時代も変わりません。
無着先生も幸四郎氏も、そういったものに振り回されたという悔しさや後悔、悲しみを味わったからこそ、自分の頭で考える大切さが身に沁みていたのではないでしょうか。
戸田:今、思い返してみても、幸四郎は高圧的な体制や権威主義などに人一倍敏感なところがありました。
ー 人間が自分の頭で考えるのをやめて、強いもの・長いものに巻かれていくことの恐ろしさを身を持って知っていたんですね。
戸田:無着先生と幸四郎では、歩んできた道のりがまったく違います。
だけど、僭越ながらどこか響き合うものがあったんじゃないかと、私も感じています。
幸四郎が学びに関する絵本を作り始めたのも、子どもたちに自分の頭で考えられる人間になって、心豊かに生きて欲しいという願いがあったからだと思います。
※無着成恭氏:1927年、山形県本沢村の沢泉寺に生まれる。
1948年に山形師範学校を卒業。山形県山元村立山元中学校に着任。
戦後の民主主義教育の実践に取り組み、中学生の生徒たちが自らの生活の中から発見した物事を綴った「生活綴り方」が後に『山びこ学校』として出版され、全国で大きな反響を呼ぶ。
その後、私立明星学園教諭、後に教頭を務め、退職後は僧侶に。2023年に逝去。
質の良い、素材を目指す。
ー 『あいうえおえほん』出版から40数年。弊社は常に自分たちで企画・編集・制作してきました。
幼児教育専門の方についていただく訳でもなく、いわゆる〇〇式のようなメソッドを提唱してきた訳でもありません。
戸田:幸四郎も私も教育の専門家ではありません。
「これを読めば、子どもはこうなります。」と言うような提唱はできないし、そういう切り口でないモノを届けたいと思ってきました。
そもそも、戸田デザインが作っている絵本もカードも、すべて素材でしかないと思っていますから。
そもそも、戸田デザインが作っている絵本もカードも、すべて素材でしかないと思っていますから。
ー 素材でしかない…。もう少し詳しく聞かせてください。
戸田:絵本であれ何であれ、実際に読んでくれる子どもたちの感性や性格、さらにはご家庭の教育に対する考え方で使い方が変わっていくのが自然でしょ?
だからこそ、幅広く使ってもらえるように、素材として質の良いモノを届けたいと思ってきたんです。
ー 質の良さというのも多岐にわたりますが、戸田さんが大事にしていることは何ですか?
戸田:子どもにおもねない。これがまず、第一にありますね。噛み砕いて言うと、安易な子ども向け、という発想をしない。
「このあたりに可愛いイラストを入れとけば、子どもは喜ぶだろう。」「今はこういう素材が流行っているから、ひとまず使っておけばいいだろう。」とかね。
そういう発想は子どもたちの感性を軽視していないか?と疑問を感じるんです。
ー 作り手である我々大人が心から「美しい、楽しい」と思えるモノを作るべきということですね。
戸田:そういう姿勢で作らないと、子どもたちに失礼ですよね。そこに見やすさ・わかりやすさを加えて、さらに質の良い素材に仕上げていく。
これが戸田デザインの基本姿勢と思ってきました。
"もうひとつの入り口"でありたい。
ー 戸田さんはお子さんを育てられる中で、子どもたちの教育について考えることはありましたか?この点が気になるとか、もっとこうなったら良いとか、色々あると思うのですが。
戸田:うーん、難しいねぇ。
あくまで私個人の所感だけれど、教えられたことに疑問を挟まずに進める子どもたちはいいけれど、そこからはみ出ると苦労する。そう言う印象はありますね。
ー それこそ、無着先生が仰っていた分数の割り算で疑問を感じて前に進めなくなるとか?
戸田:本来、色んなことに逐一疑問を持つのは素晴らしいことなんだけどね。
でも段々と周りについていけなくなる向きはあると思います。
ー 子どもたちの学びは、基本的に学校がベースになります。
戸田:そうだね。学校というのは、たくさんの子どもたちに限られた人数の大人が教育をしていく場所。子どもたちが足並みを揃えて学んでいって、進級し、卒業していく。
学校が進めるスピードにいかについていけるか否か、それが子どもたちの評価基準となる時代は長かったと思いますよ。
ー 特に高度経済成長の時代なんかは子どもの数も多かったから、足並みを揃えることが重要視されますよね。
今は、個人の資質に目を向ける教育が重視されたりと随分変わってきたと思いますが、やはり一定の評価基準がないと難しいのも事実だと感じます。
戸田:教育システムの基本は国が作っているしね。
以前よりずっと個を大切にする流れがあるにせよ、先生はクラスの生徒全員をある程度同じ理解度まで引っ張っていかなきゃならない。
それには教科書という決まった教材があって、そこに習い、テストがあるというのは当然の流れでもあるとは思います。現場では効率化だって求められるでしょう。
ー 以前、戸田さんが「親は子どもの幸せを願って、つい多くを望んでしまう」と話していたのが印象に残っています。
戸田:根底ではその子らしく、楽しく生きてくれればいいって思っているんだけどね。
周りの子どもたちと同じことが出来て欲しいし、テストの点数も良いに越したことはないと考えてしまう時もある。それはまぁ、親心というか。
ー 当たり前ですが大人は皆、子どもだった頃があります。
自分の子ども時代を振り返ると、画一的な評価の枠の中で苦しんだり、何かしらの窮屈さを味わった人も多いはずです。
戸田:そうなんだよね。学びを通して、子どもたちが喜びを感じたり、それぞれの輝きを得ていくのが、本当は理想なんだけど。
ー その理想に近づくために、戸田デザインが微力でも力になれることって何でしょう?
戸田:子どもたちの個性も千差万別。当然ながら性格も得手・不得手もみんな違います。
全員にフィットするモノを届けるのは、正直難しいと思っています。
ただ、今の話ではないけれど、ある種のシステム化された教育にうまくハマれない…。
そう言う悩みを持っている子どもたちの小さな希望になる絵本・プロダクトだったら嬉しいなと思います。
時計の読み方がわからなかったけれど、これを読んだらスッと理解できた。そうした内容のお声を多くいただきますが、そういうことでしょうか?
戸田:最初に試した入り口がフィットしなかったからと言って、何もその子に能力がない訳ではない。自分に合う別の方法を見つければいいんです。
戸田デザインの入り口から入ってみたら、楽しかった!興味が湧いてきた!そんな存在であれたらいいよね。
ー 自分にあった選択肢が他にある。それを知るのは大切ですね。
これしかない…。と思うと身動きが取れなくなるし、そこにフィットしない自分を卑下してもしまう。これは大人でも経験することです。
【もうひとつの入り口】の存在を早めに知っておくのは、生きていくうえで助けにもなると思います。
「知育」と言う気負いを捨てる。
ー 自分たちが志すモノづくりを続けてきて、多くの方々に「初めて読むなら戸田デザイン」「学びのきっかけに最良」などというお声をいただけるようになりました。とても有難いことですね。
戸田:本当に光栄なことです。
改めて思いますが、未知のものに触れる時って、最初が肝心なんですよね。
学びもそう。英語でも地図でも、最初に「うわぁ〜。難しそうでつまらない〜。」と感じたら、好奇心が湧いてくる状態にはならない。
学びもそう。英語でも地図でも、最初に「うわぁ〜。難しそうでつまらない〜。」と感じたら、好奇心が湧いてくる状態にはならない。
どんどん受け身で知識を浴びる状態になっても、仕方ないことだと思います。
ー そこを我々はデザインのちからで切り拓きたいと思って取り組んできました。
掲載する情報を厳選し、わかりやすく・楽しく・美しく作る。
そうすることで、いわゆる暗記型の勉強に馴染めない子どもたちの【もうひとつの入り口】としても活用いただけているのは嬉しいことです。
掲載する情報を厳選し、わかりやすく・楽しく・美しく作る。
そうすることで、いわゆる暗記型の勉強に馴染めない子どもたちの【もうひとつの入り口】としても活用いただけているのは嬉しいことです。
戸田:でも、これが不思議なもので…。
【もうひとつの入り口】として楽しく読める・遊べるモノを目指すと、広く色んな子にわかりやすく、楽しめるモノになるんだよね。
お客さまからいただく感想も、本当にたくさんのバリエーションがあるでしょ?
ー 同じ絵本に対しても、ある意味、真逆の感想をいただくことも多々あります。
「学校の勉強ではついていけなかったけれど、この絵本でわかるようになりました。」
「受験のための教材として、とても役に立ちました。」とか。
「学校の勉強ではついていけなかったけれど、この絵本でわかるようになりました。」
「受験のための教材として、とても役に立ちました。」とか。
戸田:そうそう。それに自分たちが毎度驚く。これを何十年も続けています 笑。
ー ご自分の想像を超えたという点で、忘れられないエピソードってありますか?
戸田:最近だと『Baby Piece (ベビーピース)』かな。
あの木のおもちゃを作った動機って、実はとてもシンプルなんですよ。
「戸田デザインのイラストが印刷された天然木のピース。それがいっぱいあったら、すごくキレイだよな!楽しいだろうな!」出発はそれだけだから 笑。
ー 覚えています。
「絶対に子どもたちは楽しく遊ぶぞ!」と仰っていました。
「絶対に子どもたちは楽しく遊ぶぞ!」と仰っていました。
戸田:もちろん、ただ鮮やなイラストのピースだけでは玩具としては弱い部分があるから、遊びや学びが広がるように工夫はしました。
でも基本の考えは最初の動機から変わっていない。「これを学ぶために、ここはこうして」という知育面でのアプローチからは作り始めていなかったんです。
でも基本の考えは最初の動機から変わっていない。「これを学ぶために、ここはこうして」という知育面でのアプローチからは作り始めていなかったんです。
ー ピースの裏にも色があると楽しいな、しかもカテゴリーで色が別れていたら遊びやすいな、というような発想で作られいますからね。
戸田:それがいざ販売してみると、いわゆる知育の側面でも多くの支持をいただきました。
小学校受験を目指す学習教室で使っていただいたり…。まさに嬉しい驚きでした。
小学校受験を目指す学習教室で使っていただいたり…。まさに嬉しい驚きでした。
ー これは手前味噌な発言かもしれませんが、本来、そうした作り手の意図を超えた反応・広がりをいただくことが、良いモノを作れたひとつの証かもしれません。
戸田:どういうこと?
ー 例えば映画でも絵画でも、良作と呼ばれるものは様々な評価をされるものです。
評価は観る人の視点に基づきます。政治への関心が強い人はそこを基点に評価をするし、美的な視点を重視する人もいる。
評価は観る人の視点に基づきます。政治への関心が強い人はそこを基点に評価をするし、美的な視点を重視する人もいる。
戸田:作り手の考えとは別に、色んな角度から意見や批評がが飛び交うよね。
ー はい。厳しい意見も含めて、様々な評価にさらされます。
ただ、子どもに向けたモノとなると、優しさ・安全性といった部分に基軸が偏る向きもあります。さらに「知育」というジャンルになると、使い方にも絶対的な正解があるように受け取られがちです。
でも、本来もっと自由に解釈されて良いはずです。
手にした方によってさまざまに評価され、使い方も色々な方向に拡張されていく方が自然で面白いと思いますね。
手にした方によってさまざまに評価され、使い方も色々な方向に拡張されていく方が自然で面白いと思いますね。
戸田:本当にそうなんだよね。
だからこそ「子ども向け」「知育」というカテゴリーに必要以上に縛られずにモノづくりをしたいと思っています。
ー 縛られると、発想がつまらなくなりますか?
戸田:うーん、というよりね、取り繕っても仕方ないというか…。
モノを作るということは自分の内側にあるものが問われる作業だと思っているんです。
私自身が何を美しいと感じてきたか、社会にある事柄をどう考えてきたか、その上で、どういうモノを子どもたちに届けたいのか。
作ったモノを通して諸々が透けて見えると思っています。
モノを作るということは自分の内側にあるものが問われる作業だと思っているんです。
私自身が何を美しいと感じてきたか、社会にある事柄をどう考えてきたか、その上で、どういうモノを子どもたちに届けたいのか。
作ったモノを通して諸々が透けて見えると思っています。
ー 狙いみたいなものも、透けてしまう?
戸田:ええ、なんとなく計算が見え隠れしますよね。
結局のところ、美的なものであれ、考え方であれ、自分の中にないものは出せないんですよ。
結局のところ、美的なものであれ、考え方であれ、自分の中にないものは出せないんですよ。
私は、学問というのは競い合う為のものでもないと思っているし、幼い時の出来・不出来で人生は決まらないと思っています。
知識や学びは、長い人生を手探りで生きていくための灯火のようなものであって欲しいと思ってモノづくりをしてきました。
でも私の考えとは逆のところに、大きなマーケットが存在していることも事実。
知識や学びは、長い人生を手探りで生きていくための灯火のようなものであって欲しいと思ってモノづくりをしてきました。
でも私の考えとは逆のところに、大きなマーケットが存在していることも事実。
ー いわゆるお勉強の教材的なところですか?
戸田:もちろん、お勉強の教材的なものが間違っていると言うことではありません。
正しい知識を持っていることは重要だし、そのためのツールは必要でしょう。
ただ、単純に私の中で一番伝えたいことではない。それだけです。
ただ、単純に私の中で一番伝えたいことではない。それだけです。
ー 戸田さんは正解や知識を超えていくものを届けたいと考えている。
戸田:その通りです。
でもね、商売をする上でマーケットとして大きいところが気にならないと言えば嘘になる。
あえて自分が選ばなかった方に、無意識でも引っ張られては仕方ないからね。
だから常に自分の中でおかしな誤魔化しや忖度が入らないように、知育に関わるモノを作っているという余計な気負いは捨てて臨んでいる部分はあります。
だから常に自分の中でおかしな誤魔化しや忖度が入らないように、知育に関わるモノを作っているという余計な気負いは捨てて臨んでいる部分はあります。
ー 戸田さんの覚悟であり、矜持のようなものでしょうか。
そしてこれこそが「戸田デザインの目指す知育」とも言えますね。
そしてこれこそが「戸田デザインの目指す知育」とも言えますね。
戸田:なんだか、いつになく深いことを話しちゃった気がするな。実際の私より、すごい思慮深い人みたいになってない?
本当はそこまでキリキリせず、楽しく仕事をしているんだけど 笑。
ー 戸田さんの秘めたる姿勢を言葉にされた、と言う感じでよろしいのでは 笑。
戸田:笑。でも我々は、いつだって自分の内側を豊かに耕して仕事をすべきとは思っています。
そうでなければ、手にしてくれた人の心を動かすようなものは作れない。届けられない。
ー そういう気概を持って作り・販売をしているのが、戸田デザイン研究室である。
そう言い続けられるよう、スタッフ全員で努めないといけないですね。
戸田:うん、そういうこと!